女優として長年活躍してきた市毛良枝さん。
そんな市毛さんですが、母親の介護で心の限界を感じたことがあるのでしょうか?
市毛さんは「徹子の部屋」に出演し、13年間にわたる母親の介護について語りました。
母親の脳梗塞や骨折、リハビリなどを経験し、心が限界を迎えた時期があったそうです。
今回は、市毛さんの介護経験と、そこから得た学びについて詳しく見ていきましょう。
市毛良枝の母親の介護経験

市毛さんの母親の介護はどのようなものだったのでしょうか?
13年間という長期にわたる介護の中で、様々な困難があったようです。
①
市毛さんの母親は100歳で亡くなるまで、市毛さんが介護を続けていました。
その間、母親は2度の脳梗塞を経験し、大腿骨骨折も患いました。
医師からは「歩けなくなる可能性がある」と言われたこともあったそうです。
②
しかし、母親は驚くべき回復力を見せ、90代でも海外旅行に行けるまでに回復しました。
市毛さんは「(母が)ヒラメ筋がつくほどにリハビリを楽しんでいた」と語っています。
➂
介護の日々は決して楽ではありませんでした。
市毛さんは仕事との両立に苦労し、「一人娘だから頑張らなければ」というプレッシャーに追われていたと振り返っています。
④
しかし、母親の前向きな姿勢や、周囲の支えによって乗り越えることができたようです。
市毛さんは「母は、暮らしの中で”楽しむ”ことをあきらめなかった人だった」と語り、その姿勢から多くを学んだと話しています。
市毛さんの介護経験は、困難を乗り越え、母親との絆を深めた貴重な時間だったようです。
1. 「介護は“奉仕”ではなく“共に生きる時間”」
「介護というと、“尽くす・犠牲になる”というイメージがありますが、
本当は“いまを一緒に生きる時間”なんです。
母を支えるようでいて、母が私を支えてくれていた。」
— 出典:サライ.jp(2024年12月掲載)
📘 解説:
市毛さんは、介護を「片方が支える」関係ではなく、**お互いが支え合う“共生の時間”**として捉えています。
介護によって「人の弱さと優しさ、両方を見ることができた」とも語っています。
2. 「“我慢する介護”では続かない」
「自分を犠牲にして頑張ると、心がすり減ります。
私は途中で心が壊れかけて、3時間泣き続けた日もありました。
その時、『このままでは共倒れになる』と思ったんです。」
— 出典:テレビ朝日『徹子の部屋』(2025年10月放送)
📘 解説:
“介護うつ”に陥りかけた経験から、**「頑張りすぎず、頼ることが必要」**と痛感。
その後は介護ヘルパーを利用し、友人や趣味の時間も意識的に持つようにしたそうです。
市毛良枝が経験した心の限界とは

市毛さんはどのような場面で心の限界を感じたのでしょうか?
介護の長期化による疲労や、感情を抑え込むことによるストレスがあったようです。
①
市毛さんは、ソーシャルワーカーとの面談中に「気づけば3時間も涙が止まらなかった」というエピソードを語っています。
この出来事は、市毛さんが心の限界を感じた象徴的な場面だったようです。
②
介護をしていると、趣味や仕事の時間が制限されることへのストレスがありました。
また、「あなたのせいで私はこんなに大変なのに」という思いを抱きながらも、それを母親に言えないというジレンマも抱えていたそうです。
➂
市毛さんは「このままではいけない」と感じ、自分自身のケアや介護以外の生活・気持ちの整え方を考え直すきっかけになったと語っています。
④
具体的には、社交ダンス・ボイストレーニング・マッサージという「トライアングル・ローテーション」を設け、自分をリフレッシュする時間を作りました。
また、友人に愚痴をこぼすことで気持ちを軽くするなど、心のケアにも努めたそうです。
市毛さんの経験は、介護者自身のケアの重要性を示しています。
心の限界を感じたからこそ、新たな対処法を見出すことができたのかもしれません。
3. 「母を通じて、“生きるリズム”を取り戻した」
「母を支えることで、私自身が“生きるリズム”を取り戻した気がします。
山を歩いたり、歌をうたったりして、体を整えることで、心も整う。
介護と生きることは、実はつながっているんです。」
— 出典:NHK『こころの時代』(2022年放送)
📘 解説:
登山やヨガなど、自然と体を使う時間を通して、**「介護も人生の一部として受け入れる」**ようになったと語っています。
4. 「母を通して“死”を学び、“生”を学んだ」
「母が亡くなったとき、悲しいというより“やり切った”という気持ちでした。
でも時間がたつと、『ああすればよかった』という思いも出てくる。
それが“生きる”ということなんでしょうね。」
— 出典:サライ.jp(2024年12月)
📘 解説:
介護を通して、**「生と死のつながり」や「後悔もまた愛の一部」**という深い人生観を得たことを語っています。
市毛良枝が介護から学んだこと

市毛さんは介護を通じて、どのような学びを得たのでしょうか?
母親の前向きな姿勢や、介護を通じて得た新たな視点について語っています。
①
市毛さんは、母親の「楽しむことを諦めない」姿勢から多くを学んだと語っています。
98歳ごろまで活発だった母親は、介護が必要になっても旅行を楽しむなど、生きる喜びを失わなかったそうです。
②
特に印象的だったのは、90代で行った海外旅行のエピソードです。
日本にいる時は「はい/いいえ」でしか会話しなかった母親が、旅先では文章のように話すようになったといいます。市毛さんは「老いても、刺激・感動を与えることは大切だ」と実感したそうです。
➂
また、介護を通じて「自分ひとりで抱え込まず、変化を起こそう」という自覚も生まれました。
周囲に助けを求めることの大切さや、介護者自身のケアの重要性を学んだと語っています。
④
さらに、市毛さんは「介護者として」だけでなく「ひとりの人間として」どう生きるかを考えるようになったといいます。
介護と自分の人生のバランスを取ることの大切さを実感したようです。
市毛さんの経験は、介護が単なる負担ではなく、人生の学びの場にもなり得ることを示しています。
困難を乗り越えることで得られた気づきは、市毛さんの人生観を豊かにしたのではないでしょうか。
市毛良枝さんの結論
「介護は、“誰かのため”に見えて、“自分を知る旅”でもあります。
逃げてもいいし、泣いてもいい。
でも、向き合うと、きっと自分の心が広がるんです。」
📘 要約すると:
- 無理をしない介護がいちばん長続きする
- 自分を整えることで相手にも優しくなれる
- 介護は「終わり」ではなく「生き方の一部」
まとめ
市毛良枝さんの13年間にわたる母親の介護経験は、困難と学びの連続でした。
心の限界を感じながらも、母親の前向きな姿勢や周囲のサポートによって乗り越えることができました。
介護から学んだ「楽しむことを諦めない」「自分自身のケアの重要性」などの教訓は、多くの人の心に響くものでしょう。
これからも市毛良枝さんのご活躍を応援していきましょう。
それではありがとうございました。
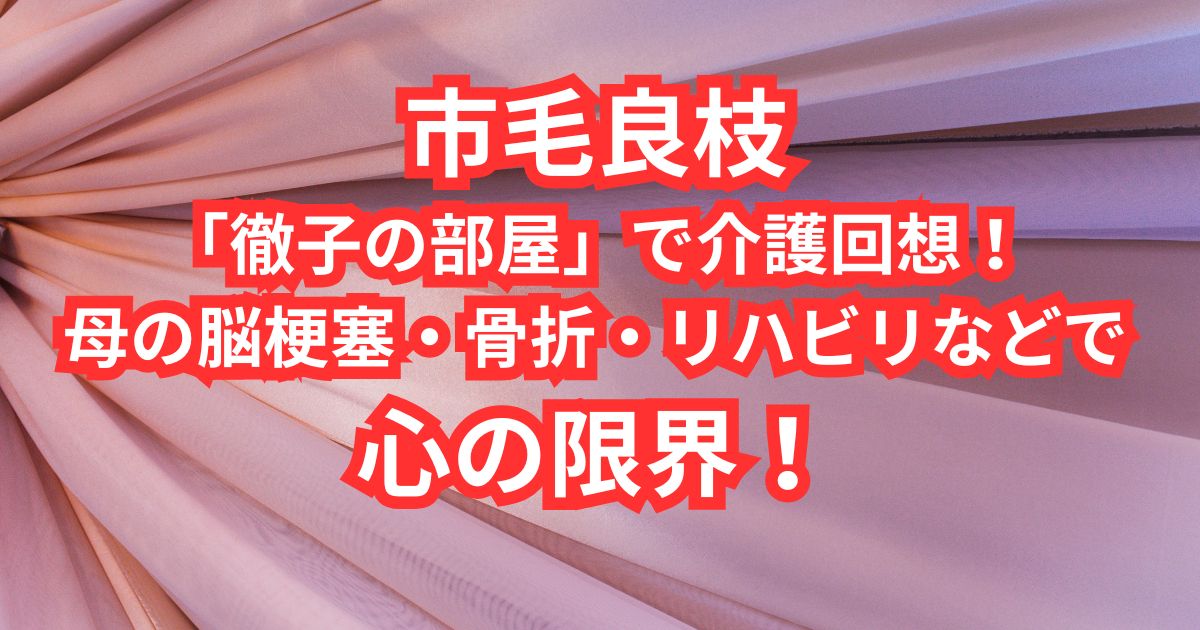








コメント